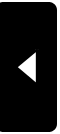2007年02月17日22:04

河合継ぎ手、と言うそうです。この継ぎ手の特徴は、継ぎ手にもなるし、仕口にもなるところです。

継ぎ手、組み合わさり前の状態です。

継ぎ手組み

仕口組み合わさり前。 木材の、同じ加工形状で、継ぎ手及び仕口が組めます。

仕口組
すごい組み方を考え出した、ものですね。河合さん という職人が、考え出したんでしょうね、きっと、...すごい職人技です。
でも、今の現場では、こういった組み方は、ほとんどやりません。
昔の職人は、こういった職人技を、競ったんでしょうね...
世界の、トップレベルにある、日本の木材加工技術、受け継いでいきたい、ものですね!
◆木造のユニットハウスなんてどうかな 新着記事
>>最新画像の一覧を見る ¦>>ブログの記事一覧を見る
ブログマイアルバム ブログ記事写真のアルバム集ですね!!
ブログマイマップ 三ヶ日町のマニアックな場所への地図情報を検索できます。
河合継ぎ手≫
カテゴリー │◆ 木組み

河合継ぎ手、と言うそうです。この継ぎ手の特徴は、継ぎ手にもなるし、仕口にもなるところです。

継ぎ手、組み合わさり前の状態です。

継ぎ手組み

仕口組み合わさり前。 木材の、同じ加工形状で、継ぎ手及び仕口が組めます。

仕口組
すごい組み方を考え出した、ものですね。河合さん という職人が、考え出したんでしょうね、きっと、...すごい職人技です。
でも、今の現場では、こういった組み方は、ほとんどやりません。
昔の職人は、こういった職人技を、競ったんでしょうね...
世界の、トップレベルにある、日本の木材加工技術、受け継いでいきたい、ものですね!
◆木造のユニットハウスなんてどうかな 新着記事
>>最新画像の一覧を見る ¦>>ブログの記事一覧を見る
ブログマイアルバム ブログ記事写真のアルバム集ですね!!
ブログマイマップ 三ヶ日町のマニアックな場所への地図情報を検索できます。
この記事へのコメント
昔、古川町(現飛騨市)の継ぎ手の博物館に訪れたことがあります。
パズルのような継ぎ手に、ただただ感心するばかり。
昔の人の技術(こだわり?)には、頭が下がります。
パズルのような継ぎ手に、ただただ感心するばかり。
昔の人の技術(こだわり?)には、頭が下がります。
Posted by いいめぬ at 2007年02月18日 21:06
ここまで やるかって
すごい 継ぎ手ですね
釘やビスを使わないでも
ぴたっと 納まり くるいも来ない
という事でしょうか
宮大工さんたちの 世界ですか?
すごい 継ぎ手ですね
釘やビスを使わないでも
ぴたっと 納まり くるいも来ない
という事でしょうか
宮大工さんたちの 世界ですか?
Posted by げんき at 2007年02月19日 18:27
いいめぬ さん
>昔、古川町(現飛騨市)の継ぎ手の博物館に訪れたことがあります。
そんな博物館があったんですか...! 知りませんでした。
機会があれば、行ってみたいと思います。飛騨には、合掌造り、高山の屋台等木工技術では、有名なものがありますので、是非行ってみたいですね。
げんき さん
>釘やビスを使わないでも
>ぴたっと 納まり くるいも来ない
>という事でしょうか
そうですね、ぴたっと 収まり くるいも来ない、木組みは理想ですね。
昔の職人さんの、木組みに対する考え方は、
「ぴたっと 収まり くるいも来ない」と言うよりは、
「きちっと収まり、抜けにくい」と言った方が、しっくりくるように思います。
木は、生き物ですので、いくら、ぴたっと収めても、多少収縮します。
木材の柔軟性、靭性を考えた、抜けにくく、柔らかでしなやかな、収まり
とでも、言いますか....?
そんな感じです。 説明が下手で、申し訳ありません。
>昔、古川町(現飛騨市)の継ぎ手の博物館に訪れたことがあります。
そんな博物館があったんですか...! 知りませんでした。
機会があれば、行ってみたいと思います。飛騨には、合掌造り、高山の屋台等木工技術では、有名なものがありますので、是非行ってみたいですね。
げんき さん
>釘やビスを使わないでも
>ぴたっと 納まり くるいも来ない
>という事でしょうか
そうですね、ぴたっと 収まり くるいも来ない、木組みは理想ですね。
昔の職人さんの、木組みに対する考え方は、
「ぴたっと 収まり くるいも来ない」と言うよりは、
「きちっと収まり、抜けにくい」と言った方が、しっくりくるように思います。
木は、生き物ですので、いくら、ぴたっと収めても、多少収縮します。
木材の柔軟性、靭性を考えた、抜けにくく、柔らかでしなやかな、収まり
とでも、言いますか....?
そんな感じです。 説明が下手で、申し訳ありません。
Posted by rebox at 2007年02月20日 00:08
充分 理解できる 説明です
ありがとうございます。m(_ _)m
ありがとうございます。m(_ _)m
Posted by げんき at 2007年02月20日 20:25
初めまして、サンパワーです。
よろしくお願いします。
「継ぎ手」と「仕口」の両方可能な切り口に感動しました。。
現在の職人は、ほとんどやらなくなったとは・・・。
残念?耐久面でやらなくなったのでしょうか。
このサイトで勉強になりましたことをお伝え
したかったので、コメントしました。
では。また訪問します。^^
よろしくお願いします。
「継ぎ手」と「仕口」の両方可能な切り口に感動しました。。
現在の職人は、ほとんどやらなくなったとは・・・。
残念?耐久面でやらなくなったのでしょうか。
このサイトで勉強になりましたことをお伝え
したかったので、コメントしました。
では。また訪問します。^^
Posted by サンパワー at 2008年08月20日 15:11
> サンパワー さん
はじめまして、コメントありがとうございます。
耐久性の面ではないですね! 手間が掛かるかどうか...そのような観点で
やらなくなってしまったのでしょうね~~おそらく・・・?
他にもいろいろな優れた、継ぎ手仕口があります。
そういった昔の職人さんの技術を、今勉強中です。 面白いですね!!
> では。また訪問します。^^
よろしくお願いいたします。
はじめまして、コメントありがとうございます。
耐久性の面ではないですね! 手間が掛かるかどうか...そのような観点で
やらなくなってしまったのでしょうね~~おそらく・・・?
他にもいろいろな優れた、継ぎ手仕口があります。
そういった昔の職人さんの技術を、今勉強中です。 面白いですね!!
> では。また訪問します。^^
よろしくお願いいたします。
Posted by rebox at 2008年08月20日 23:04
at 2008年08月20日 23:04
 at 2008年08月20日 23:04
at 2008年08月20日 23:04