2013年04月12日09:05

食べて、祈って、恋をして・・・の映画原作者 エリザベス・ギルバート
の ” 創造性をはぐくむには・・・ ” の言葉です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
クリエイティブな仕事をやっている方たちの悩み不安・・・
それは、今の自分を超えられるのか・・・?
次の作品は・・・前回の作品を超えられるのか・・・?
想像に苦悩はつきものであり、ある有名な作家は、 「自分の作品にじわりじわりと、
追いつめられる・・・」 そんな言葉を残し、自殺した人がいるそうです。 そんな
芸術家・・・と言われる作家も含め、多くの方たちはいったいどんな想像しているのか・・・?
芸術性は、最終的に必ず苦痛をもたらすと・・・?
芸術家、創作者が最終的に行き着くところはどこか・・・?
・・・と考えたそうです。

その答えのヒントが、 古代ギリシャとローマにあったそうです。
古代ギリシャ と ローマ時代の人々には、創造性が人にあるとは信じられていなかった
とのことです。 創造性は、人に付き添う精霊で遠く未知の世界から来た・・・
古代ギリシャ人は精霊を ダイモン と呼びました。
ソクラテス は ダイモン がついていると信じていた。
◆ ダイモン
http://www.jiten.info/dic/daimon.html
◆ ギリシア人の霊魂観にある、守護霊の総称
http://red.sakura.ne.jp/~co-wards/explain/term/daemon.html
遠くから叡智を語ってきたと・・・ ローマ人も同じでしたが、肉体のない創造の霊を
ジーニアス(天才)と呼びました。 彼らは、肉体のないジーニアスを能力のある個人とは
考えなかった、あの精霊の事だと考えていた。 その精霊たちは、創作活動をこっそり手伝い
たとえば、過剰な自惚れから立派な作品ができても・・・これは、自分だけの功績ではない。
霊が助けたからだ・・・逆に・・・失敗しても自分だけのせいじゃない・・・
ジーニアスが失敗したんだ・・・ 自分以外に責任転嫁できる・・・(笑)

これは、長らく西洋に浸透していましたが、ルネッサンスがすべてを変えました。
世界の中心に、人間を置こうじゃないか・・・そのような考え方の元 古代の人には、
精霊 も 神も当たり前に身近にいた存在であったものが、ルネッサンス以降
神の声を伝える謎の生き物の存在は消え、合理的人文主義が誕生した。
そして、芸術家が ジーニアス(天才) と 称賛されるようになったと・・・
古代では、ジーニアスという存在が、個人とは別に存在していたものが
個人が ジーニアス(天才) になってしまった。
ジーニアス が そばにいるという存在ではなく、個人そのものが
ジーニアスであると・・・これは大きな間違いです。
何か創ろうとした人ならわかる、なんとなくでも・・・ 非合理的な・・・
時に、 超常現象とさえ感じる・・・ 「天から創造性が降ってくる・・・」
おぉぉ~~ 神よ!!

こんな話もあります。 北アフリカの砂漠では、月夜に踊りの祭典があります
明け方まで何時間も踊るのです・・・
たまに、 ごくまれに 踊り手が一線を超える時があるそうです。
いつもの踊りと変わらないはずなのに、なぜか周囲と符合する。
周りの 自然、人々、空気と一体となって 突然人には見えなくなる・・・
足元から、体の内側から神々しく 燃え上がるんです。
太古の人々は、 そんなとき 何が起きたのか わかっていました。
自分たちの 普段からの体験を通して、何が起こっているのか理解していたんでしょうね~
そんなとき、周りの人々は、両手を合わせ唱え始めます。
アラー アラーの神よ・・・神よ!! なんて、掛け声をかけるそうです。
「いいぞ~」 とか・・・ 「がんばれ~」 という意味での掛け声だそうです。
この掛け声が・・・ アラー が オレー に変化したものらしいですね~
これが・・サッカーの 掛け声で・・・ オ レーオ レ オ レ オ レー の掛け声に
代わっていったとのことです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日本でも、全国各地で朝まで踊り続ける伝統文化がありますが、
それも、ルーツは、同じなんでしょうね~ 引佐の ひよんどり とか・・・ 水窪の田楽 とか・・・
周りの自然、人々、空気と一体となって・・・
突然人には見えなくなり・・・
足元から、体の内側から神々しく、燃え上がる・・・
そんな体験を通して、人間 と 神様の存在・・・? を認識したんでしょうかねぇ~・・・
エリザベス・ギルバート 原作の映画 「食べて、祈って、恋をして」
エリザベス・ギルバート・・・本人自身の自伝を、小説にしたそうです。
心の赴くままに旅をする・・・
心を空っぽにして・・・入り口を作る・・・
そこに、宇宙がなだれ込む・・・
そのとき、君は愛で満たされる・・・
そこからまた新たな旅が始まる・・・
こんな、フレーズで映画が紹介されています。
まだ映画は見たことありませんが・・・
心の旅は、身近な・・・どこでも・・・手に入るのかもしれませんね~
自分の考え方・・・心の在り方次第で・・・
◆ エリザベスギルバート 「創造性をはぐくむには・・・」
http://www.ted.com/talks/lang/ja/elizabeth_gilbert_on_genius.html
◆木造のユニットハウスなんてどうかな 新着記事
>>最新画像の一覧を見る ¦>>ブログの記事一覧を見る
ブログマイアルバム ブログ記事写真のアルバム集ですね!!
ブログマイマップ 三ヶ日町のマニアックな場所への地図情報を検索できます。
食べて、祈って、恋をして≫
カテゴリー │ ● 本・映画・美術等

食べて、祈って、恋をして・・・の映画原作者 エリザベス・ギルバート
の ” 創造性をはぐくむには・・・ ” の言葉です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
クリエイティブな仕事をやっている方たちの悩み不安・・・
それは、今の自分を超えられるのか・・・?
次の作品は・・・前回の作品を超えられるのか・・・?
想像に苦悩はつきものであり、ある有名な作家は、 「自分の作品にじわりじわりと、
追いつめられる・・・」 そんな言葉を残し、自殺した人がいるそうです。 そんな
芸術家・・・と言われる作家も含め、多くの方たちはいったいどんな想像しているのか・・・?
芸術性は、最終的に必ず苦痛をもたらすと・・・?
芸術家、創作者が最終的に行き着くところはどこか・・・?
・・・と考えたそうです。

その答えのヒントが、 古代ギリシャとローマにあったそうです。
古代ギリシャ と ローマ時代の人々には、創造性が人にあるとは信じられていなかった
とのことです。 創造性は、人に付き添う精霊で遠く未知の世界から来た・・・
古代ギリシャ人は精霊を ダイモン と呼びました。
ソクラテス は ダイモン がついていると信じていた。
◆ ダイモン
http://www.jiten.info/dic/daimon.html
◆ ギリシア人の霊魂観にある、守護霊の総称
http://red.sakura.ne.jp/~co-wards/explain/term/daemon.html
遠くから叡智を語ってきたと・・・ ローマ人も同じでしたが、肉体のない創造の霊を
ジーニアス(天才)と呼びました。 彼らは、肉体のないジーニアスを能力のある個人とは
考えなかった、あの精霊の事だと考えていた。 その精霊たちは、創作活動をこっそり手伝い
たとえば、過剰な自惚れから立派な作品ができても・・・これは、自分だけの功績ではない。
霊が助けたからだ・・・逆に・・・失敗しても自分だけのせいじゃない・・・
ジーニアスが失敗したんだ・・・ 自分以外に責任転嫁できる・・・(笑)


これは、長らく西洋に浸透していましたが、ルネッサンスがすべてを変えました。
世界の中心に、人間を置こうじゃないか・・・そのような考え方の元 古代の人には、
精霊 も 神も当たり前に身近にいた存在であったものが、ルネッサンス以降
神の声を伝える謎の生き物の存在は消え、合理的人文主義が誕生した。
そして、芸術家が ジーニアス(天才) と 称賛されるようになったと・・・
古代では、ジーニアスという存在が、個人とは別に存在していたものが
個人が ジーニアス(天才) になってしまった。
ジーニアス が そばにいるという存在ではなく、個人そのものが
ジーニアスであると・・・これは大きな間違いです。
何か創ろうとした人ならわかる、なんとなくでも・・・ 非合理的な・・・
時に、 超常現象とさえ感じる・・・ 「天から創造性が降ってくる・・・」
おぉぉ~~ 神よ!!

こんな話もあります。 北アフリカの砂漠では、月夜に踊りの祭典があります
明け方まで何時間も踊るのです・・・
たまに、 ごくまれに 踊り手が一線を超える時があるそうです。
いつもの踊りと変わらないはずなのに、なぜか周囲と符合する。
周りの 自然、人々、空気と一体となって 突然人には見えなくなる・・・
足元から、体の内側から神々しく 燃え上がるんです。
太古の人々は、 そんなとき 何が起きたのか わかっていました。
自分たちの 普段からの体験を通して、何が起こっているのか理解していたんでしょうね~
そんなとき、周りの人々は、両手を合わせ唱え始めます。
アラー アラーの神よ・・・神よ!! なんて、掛け声をかけるそうです。
「いいぞ~」 とか・・・ 「がんばれ~」 という意味での掛け声だそうです。
この掛け声が・・・ アラー が オレー に変化したものらしいですね~
これが・・サッカーの 掛け声で・・・ オ レーオ レ オ レ オ レー の掛け声に
代わっていったとのことです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日本でも、全国各地で朝まで踊り続ける伝統文化がありますが、
それも、ルーツは、同じなんでしょうね~ 引佐の ひよんどり とか・・・ 水窪の田楽 とか・・・
周りの自然、人々、空気と一体となって・・・
突然人には見えなくなり・・・
足元から、体の内側から神々しく、燃え上がる・・・
そんな体験を通して、人間 と 神様の存在・・・? を認識したんでしょうかねぇ~・・・
エリザベス・ギルバート 原作の映画 「食べて、祈って、恋をして」
エリザベス・ギルバート・・・本人自身の自伝を、小説にしたそうです。
心の赴くままに旅をする・・・
心を空っぽにして・・・入り口を作る・・・
そこに、宇宙がなだれ込む・・・
そのとき、君は愛で満たされる・・・
そこからまた新たな旅が始まる・・・
こんな、フレーズで映画が紹介されています。
まだ映画は見たことありませんが・・・

心の旅は、身近な・・・どこでも・・・手に入るのかもしれませんね~
自分の考え方・・・心の在り方次第で・・・

◆ エリザベスギルバート 「創造性をはぐくむには・・・」
http://www.ted.com/talks/lang/ja/elizabeth_gilbert_on_genius.html
◆木造のユニットハウスなんてどうかな 新着記事
>>最新画像の一覧を見る ¦>>ブログの記事一覧を見る
ブログマイアルバム ブログ記事写真のアルバム集ですね!!
ブログマイマップ 三ヶ日町のマニアックな場所への地図情報を検索できます。







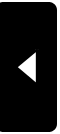

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。